【この記事でわかること】
- プロテインが「腎臓に悪い」と言われる理由
- 科学的根拠からみた「本当に危険なのか?」
- 腎臓に負担をかけないプロテインの飲み方
- 腎臓病や生活習慣病の人が注意すべきポイント
筋トレやダイエットのために、プロテインを飲む人が増えています。
一方で、「プロテインは腎臓に悪いらしい」という話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
実際、たんぱく質を多く摂ると腎臓が“働きすぎ”の状態になることがあります。しかし、科学的な研究では「健常者であれば、適量のプロテイン摂取で腎臓に深刻な悪影響はない」とも報告されています。
この記事では、最新のエビデンスをもとに、「どこまでが安全なのか」「腎臓を守るためにできる工夫は?」
をわかりやすく解説します。
プロテインブームと腎臓への不安

筋トレをしている人だけでなく、「健康維持」や「美容目的」でプロテインを飲む人が急増しています。
しかし、その一方で「プロテインは腎臓に悪い」「飲みすぎると腎臓が壊れる」という話も耳にします。この不安のもとになっているのは、たんぱく質の代謝と腎臓の働きです。
腎臓は、体の中の老廃物をろ過して尿として排出する臓器。
たんぱく質を多く摂ると、分解によって「尿素」などの老廃物が増え、腎臓が処理しなければならない量も増えます。
このため「高たんぱく=腎臓に負担をかける」というイメージが広がったのです。
しかし、実際のところ、健常者(腎臓が正常に働いている人)においては、プロテイン摂取がすぐに腎臓を悪化させるという科学的証拠はほとんどありません。
科学的にみたプロテインと腎臓の関係
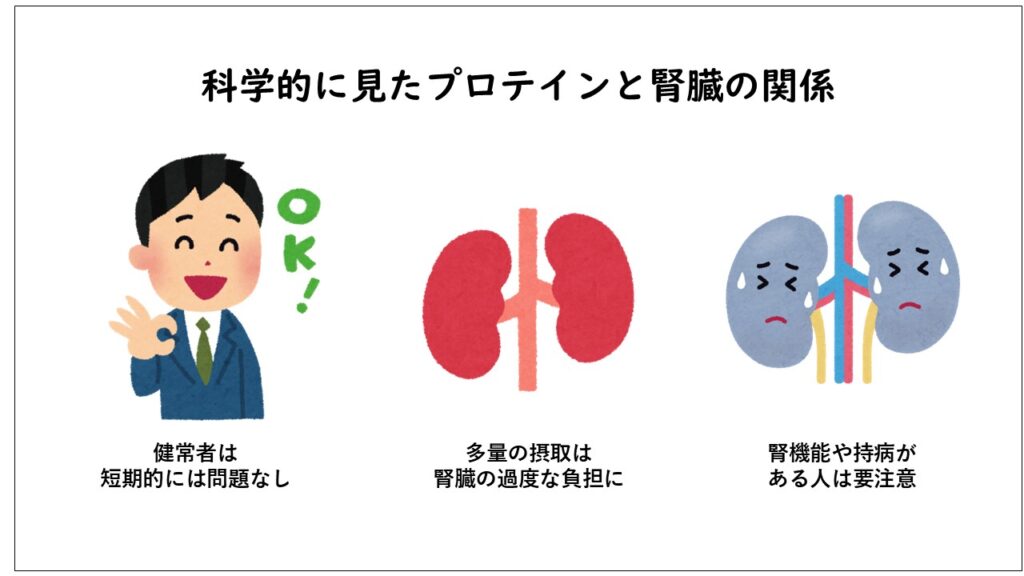
健常者では短期的な有害性は少ない
カナダの研究者 Devries ら(2018, Journal of Nutrition)によるメタ解析では、健常成人における高たんぱく食と腎機能(糸球体ろ過率:GFR)の関係を分析した結果、短期間では腎機能の悪化を示す証拠は見られなかったと報告されています。
つまり、健康な人が適量のプロテインを摂取する分には、腎臓に大きな問題は起きにくいというのが現時点での科学的な見解です。
メタ解析とは、複数の研究結果を統計的にまとめて、全体としての傾向や効果を明らかにする方法です。
過濾過とは?腎臓が「働きすぎる」状態
一方で、プロテインなどを多く摂ると、一時的に腎臓の働きが活発になり「過濾過(かろか)」という状態が起こります。
これは、腎臓が“フル回転”で老廃物を処理している状態を指します。
短期間であれば生理的な反応の範囲内ですが、この状態が長く続くと、腎臓のろ過機能を担う“糸球体”という構造に負担がかかり、将来的に慢性腎臓病のリスクが上がる可能性があると考えられています。
韓国のKoら(2020, Nutrients)のレビューでは、動物実験や臨床データをもとに「高たんぱく摂取による糸球体内圧の上昇と過濾過が腎障害を引き起こすメカニズム」を解説しています。
つまり、短期間では問題なくても、“過剰かつ長期的な摂取”が腎臓にストレスを与えるリスクがあるということです。
レビューとは、あるテーマについて過去の研究を集め、内容を整理・比較しながら全体の傾向や課題をまとめた論文のことです。
腎疾患リスクがある人は注意が必要
健康な人では大きな問題は少ないとされていますが、
- もともと腎臓が弱っている人
- 糖尿病・高血圧などの持病がある人
は注意が必要です。
米国ハーバード大学のKnightら(2003, Annals of Internal Medicine)の研究では、軽度の腎機能低下を持つ女性では、高たんぱく食が腎機能の悪化を早める可能性があると報告されました。
つまり、「健康な人」と「腎機能が低下している人」とでは、プロテインの影響が異なるのです。
血圧が高く、困っているならストレッチをしましょう。ストレッチはリラックス効果や血流促進効果があり、血圧の改善に有効です。下記の記事で紹介しているストレッチを行いましょう!

腎臓に負担をかけないプロテインの摂り方

プロテインは体づくりに欠かせない栄養素ですが、摂り方を間違えると腎臓に余計な負担をかけてしまうことがあります。
ここでは、科学的根拠に基づいた「腎臓に優しいプロテイン摂取のポイント」を紹介します。
① たんぱく質の摂取量は「体重×1〜1.6g」が目安
健康な成人では、1日あたり 体重1kgにつき1〜1.6g のたんぱく質が適量とされています。
たとえば体重70kgの人なら、1日70〜110g程度です。筋トレをしている人でも2g/kgを大きく超える必要はありません。
たんぱく質は食事からも摂れるため、プロテインドリンクは“補助”として利用する のが基本です。1日に複数回飲むよりも、トレーニング後や朝食時など「筋肉の合成が活発なタイミング」に取り入れると効果的です。
食事で肉・魚・卵をしっかり摂れている日は、無理にプロテインを追加する必要はありません。
科学的にもたんぱく質が豊富な食品を摂って筋トレを行えば、筋肉が大きくなることが認められています。詳細は下記のページで紹介しています!

② 動物性と植物性をバランスよく
たんぱく質の“種類”にも注目しましょう。
- 動物性プロテイン(ホエイ・カゼインなど)
吸収が速く、筋肉づくりに優れていますが、窒素量が多く腎臓への負担がやや大きめ。 - 植物性プロテイン(ソイ・えんどう豆など)
吸収は穏やかですが、腎臓にやさしく、血糖や脂質代謝の改善にも効果があると報告されています。
理想は「朝にホエイ、夜にソイ」など、使い分けること。
動物性と植物性を組み合わせることで、筋肉にも腎臓にもやさしい栄養バランスになります。
大豆由来のプロテインは腎疾患患者の食事療法にも使われることがあり、腎臓の酸化ストレスを軽減する可能性があると報告されています(Ko et al., Nutrients, 2020)。
*酸化ストレスとは、体の中で発生する「活性酸素(フリーラジカル)」が増えすぎて、細胞や血管、DNAなどを傷つけてしまう状態のことです。
下記の記事では、植物性プロテインと動物性プロテインについてまとめた論文を翻訳・要約し紹介しています。植物性プロテインと動物性プロテインを詳しく知りたい方必見です!

③ 水分をこまめに摂る
たんぱく質を分解すると「尿素」「クレアチニン」などの老廃物が増えます。
これを体外に出すのが腎臓の仕事。水分が不足すると老廃物が濃くなり、腎臓への負担が増すことがあります。
- 目安は1日 1.5〜2リットル(運動量が多い人はもう少し多めに)
- コーヒー・お茶などカフェインを含む飲料だけでなく、純粋な水を意識的に飲む
「プロテインを飲む=水分をとるチャンス」と考えるのがおすすめ。1杯のプロテインに対して、もう1杯の水をセットで飲む習慣をつけましょう。
日本人は元々水分摂取量が少ないとされています。水分不足は腎臓だけでなく、美容にも悪影響を及ぼします。水分補給の大切さは下記の記事で詳しく紹介しています!
④ 摂取タイミングと“腎臓の休息”
腎臓は24時間働き続けている臓器ですが、常に高たんぱく状態が続くと疲弊しやすくなります。
1日の中で「摂取→休息」のリズムをつけることで、腎臓にも回復の時間ができます。
- 就寝直前に大量のプロテインを摂るのは避ける(寝ている間も腎臓が働き続けるため)
- 朝食や運動後など、代謝が高まっている時間帯に摂取すると効率的
夜にたんぱく質を摂る場合は、量を半分にして消化吸収の良いホエイにするのがおすすめ。
⑤ サプリメントの“多用”は避ける
プロテインだけでなく、BCAA・EAA・クレアチンなどを併用している人も多いですが、これらも腎臓が処理する窒素量を増やす要因となります。
短期間の使用なら問題はありませんが、長期的に高用量を続けると腎臓が疲れやすくなる可能性があります。
- 「プロテイン+通常の食事」で十分な人がほとんど
- 複数のサプリを使う場合は、総たんぱく量を把握しておくこと
「サプリで摂る量 > 食事で摂る量」になっている場合は要注意。腎臓のためにも、まずは食事からのたんぱく質を基本にしましょう。
⑥ 定期的に健康診断を受ける
プロテインを毎日飲む人ほど、年に1回は「腎臓チェック」を行うことをおすすめします。
血液検査の クレアチニン値(Cr) や eGFR(推算糸球体ろ過率) を確認することで、腎機能の状態がわかります。
早期に異常が見つかれば、食生活を調整するだけで改善するケースもあります。
eGFRが60未満を下回ると「軽度の腎機能低下」とされます。この段階で医師に相談すれば、進行を防ぐことができます。
動画で一緒に!腎臓を守る有酸素運動
腎臓の健康には、血流を良くすることが欠かせません。中でも有酸素運動は、動脈硬化を防ぎ、腎臓の血流を保つ効果があると報告されています。
動脈硬化が進むと、腎臓に送られる血液が減り、老廃物をろ過する力が低下します。つまり、血管を健康に保つことが腎臓を守ることにつながるのです。
ウォーキングなど軽い有酸素運動は、血圧を安定させ、糖尿病や腎臓病の予防にも役立ちます。
私のYouTubeチャンネルでは、自宅で行える有酸素運動の動画を紹介しています。リズミカルに動き、血流を改善して腎臓の負担を減らしましょう。
まとめ|腎臓を守りながらプロテインを上手に活用しよう
- 健常者では短期間で明確な悪影響は少ないが、過剰摂取や長期使用は注意が必要
- 腎疾患リスクがある人は医師の指導のもとで調整する
- 体重1kgあたり1〜1.6gを目安に、動物性・植物性をバランスよく
- 水分補給を忘れずに、腎臓を守りながら健康的に筋肉をサポート
参考文献(主要エビデンス)
- Devries MC, et al. J Nutr. 2018. Changes in Kidney Function Do Not Differ Between Healthy Adults With Higher vs Lower Protein Intakes.
- Ko GJ, et al. Nutrients. 2020. Dietary Protein Intake and the Kidney: Effects on Glomerular Filtration Rate and Mechanisms.
- Knight EL, et al. Ann Intern Med. 2003. High-Protein Diets and the Kidney.
- Van Elswyk ME, et al. Adv Nutr. 2018. The Role of Protein Source in Human Health.

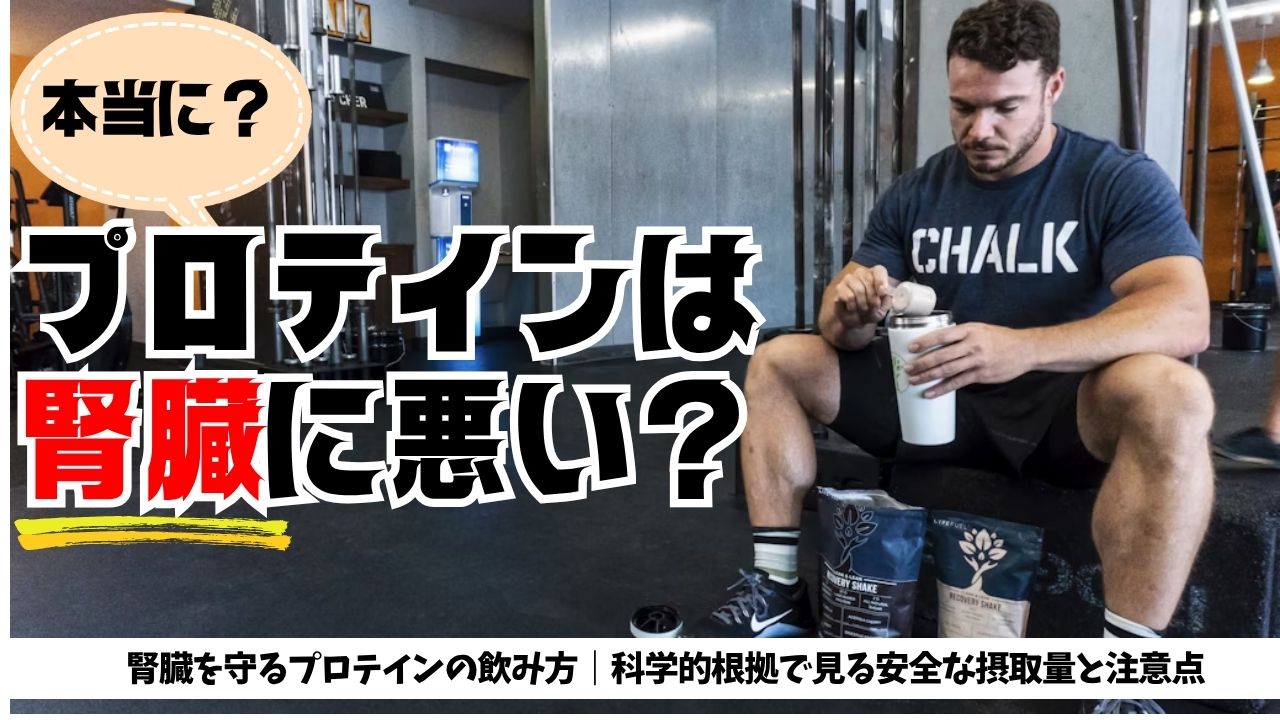








コメント